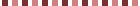
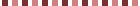
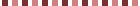
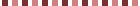
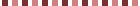
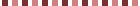
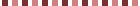
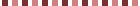
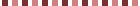
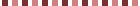
本モニタリング事業は財団法人パブリックヘルスリサーチセンターの倫理委員会での審査の結果承認され、平成18年11月から、本事業に対して理解をいただいた少数の医療機関の医師の協力を得て、同意の得られた患者さんを対象に開始されました。これまでのところ大きな問題はなくモニタリングが実施されています。
本モニタリング事業に対しては、多発性骨髄腫の患者さんを中心に、何人かの方からいくつかの質問が寄せられ始めています。また、国内でサリドマイドの申請が既に行われ、製造販売後のサリドマイドの安全管理のあり方をより明確に議論することが可能な状況になってきました。
そこで、以下に本モニタリング事業を実施することが何故必要であるかなどに関する私どもの立場・意見をより明確にさせていただくこととしました。
日本では、以下に説明するような経緯から、サリドマイドの安全管理に関しては、これまで「間接的なモニタリング」しか考えられてきませんでした。本モニタリング事業は、以下に説明する「直接的なモニタリング」が日本で成立するのか、また成立させるためにはどのような問題があるかを明らかにするために実施する試行的なものです。
| ◎ | 未承認薬と間接的なモニタリング。 |
日本臨床血液学会が平成16年12月10日に発表した「多発性骨髄腫に対するサリドマイドの適正使用ガイドライン」は、サリドマイドを使用する医師が日本臨床血液学会事務局へ、サリドマイドを使用する患者の患者イニシャル/性別/生年月日/病名の4項目を登録することを求めています。
現在、厚生労働科学研究「未承認医薬品の管理・安全性確認システムに関する研究」において進められているSafety Management System for Unapproved Drugs (SMUD)は、この日本臨床血液学会ガイドラインに沿ったシステムであり、SMUDに登録される患者IDに関する項目はガイドラインと同じく、患者イニシャル/性別/生年月日/病名の4項目に限られます。
日本臨床血液学会のガイドラインでは、患者登録を受け付けた後、医師は学会事務局に重篤な有害事象が起こったらこれを報告することになっていますが、患者さんがガイドラインで定められた必要事項(避妊など)を守っているかを事務局が確認することなどは意図されていませんし、また当然のことですが、そのための十分な予算やスタッフも用意されていません。
SMUDでは、患者登録の段階で登録する医師は「患者さんに必要な説明をしたか?」など最低限の事項に回答するように求められます。また、サリドマイド使用終了時には、担当医は患者さんのガイドラインの遵守状況などに関する回答を求められますが、これらの情報は医師を通じて得られるもので、患者IDについては、最後まで患者イニシャル、性別、生年月日、病名以外は不明です。
SMUDを含め、担当医によって間接的に患者さんのガイドラインの遵守状況などを確認するモニタリングを以下「間接的なモニタリング」と呼ぶことにします。これに対し、患者さん本人に安全管理を専門に行うセンターが連絡するか、患者さん本人がセンターに自ら連絡して、安全管理に必要な事項を実施していることを患者さん自らが申告するモニタリングを「直接的なモニタリング」と呼ぶことにします。
日本臨床血液学会に現在登録されている患者IDにしてもSMUDで登録される患者IDにしても、登録された情報だけからでは患者さん本人を特定することはできず、直接的なモニタリングにつなげることは不可能です。未承認薬については、その安全性モニタリングに責任をもつ企業が存在せず、モニタリングのシステム作成に使うことのできる財源も限られていますので、未承認薬としてのサリドマイドに関するモニタリングが担当医を通じて間接的に行われることはやむを得ないと思います。
しかし、サリドマイドが承認された後も、サリドマイドの安全性に全面的な責務をもつ企業が主治医を通じた間接的な安全性モニタリングのみしか実施しないとすれば、それは大きな問題だと考えています。
以下、その理由を説明します。
| ◎ |
サリドマイドの後世代に対する影響の回避に対して直接的責任をもつのは、
サリドマイドを使用する患者自身である。 |
サリドマイドの「催奇形性という副作用」は通常の「抗がん剤の副作用」とは明らかに異なります。特に「催奇形性」というサリドマイドがもつ有害作用を防止する直接的な責任は医師ではなく患者本人がもっている点が、有害作用の防止や早期発見や対処に医師が直接的な責任をもつ、通常の「副作用」とは大きく異なる点です。
サリドマイドの催奇形性防止の直接の責任を医師ではなく患者自身が負っている点は、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬の効果増強に果たすお酒の役割を考えれば分かりやすいかも知れません。お酒はこれらの睡眠薬の作用を増強しますので、薬を飲む場合はお酒を飲んではいけないことになっています。「お酒によって薬の作用が強くなるので飲んではいけない」ことを患者に伝えるのは、確かに医師の責任です。しかし、そのことについて医師から十分説明を聞いた患者が、それでも医師からの注意を無視して、薬を使いながら同時にお酒を飲み、結果として転倒するなど事故を起こしたとしたら、それは医師の責任でしょうか?私たちはそう思いません。
もちろん、説明したにもかかわらず、医師の忠告を無視して患者が薬とお酒を同時に飲んで危険な事態に陥ったことを知った場合、医師は再度忠告するか、あるいは「それならこの薬を出すわけには行きません」と薬の処方を控えるなどの対処をすべきでしょうが、それでも「薬を飲む以上酒を控える」という自制に直接責任をもっているのは患者自身であり、医師ではありません。
睡眠薬とお酒の問題なら、医師の忠告を無視した患者がお酒を飲んで起こした問題は「患者個人の問題」で済ますことができるかも知れません。しかしサリドマイドでは、万が一医師から説明を聞いたにもかかわらず患者がこれを無視して、とりかえしのつかない後世代への影響を残したら、それは患者個人の問題にとどまらず、社会へ重大な影響を及ぼすことを意味します。サリドマイドを使用する患者さんは、後世代に悪い影響を与える可能性のある行為を自らがしていないことを明らかにする社会的な責務を持っています。
この社会的な責務を果たすことは、それほど難しいことでも複雑なことでもなく、プライバシーが厳密に守られる仕組みの中で、サリドマイドを使用している患者さんが自ら、「サリドマイドを使用する以上守るべき責務を理解している」こと、また、自分が「後世代へ悪影響を及ぼすことは全くしていない」ことを表明することだけで十分です。サリドマイドの承認を受け、製造販売する企業は、この点をサリドマイドを使用する患者さん全員に確認し、社会に対して「全ての患者が、その社会的責任を十分理解した上で実際に責任を果たしている」ことを保証する義務があります。
| ◎ | 何故直接モニタリングが必要で間接モニタリングではだめなのか? |
サリドマイドを使用する患者の持つ、社会的責務(特に義務遂行の事実の社会への表明)を担当医に代行してもらう方法が全く成立しないというわけではありません。直接的な責任は担当医師にはありませんが、患者本人に代わって、しかるべき者(たとえば薬を製造販売する企業)に報告する、という方法も全く不可能というわけではありません。しかし、これを確実に行おうとすると、常時1000人前後に上ると推定されるサリドマイドを使用する患者さんの治療にあたる全国の医師から、患者さんの情報を間接的に、しかし確実に、企業またはしかるべき安全管理センターに伝える仕組みが必要になります。
医薬品によっては、その使用方法に高度の専門性を要し、特別の医療機関で専門医のみが使わないと治療対象の患者さん本人を傷つける可能性が高いために強い規制が必要で、単に有害作用などについての情報を伝達するだけでなく、適切な病院以外には薬の供給をしない、などの強い制限を加えることが妥当と考えられる場合もあるでしょう。
しかしサリドマイドの場合、催奇形性以外の毒性は、他の悪性疾患治療薬に比べて特段に強いというわけでもなく、「契約を結ばない医療機関に薬を供給しない」などを必要不可欠とする薬であるとは考えられません。
例えば、最近多発性骨髄腫の新しい治療薬として薬価収載されたベルケイドには、急性肺障害・間質性肺炎の副作用があり、一度この副作用が発現した患者の無視できない割合の方が不幸の転帰をとります。発売元のヤンセンは58ページに上る「適正使用ガイド」を出して、この重篤な副作用を警告し、「本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例のみに行うこと」と警告しています。
ただし、ベルケイドについては、医療機関が企業と安全管理のために特別のの契約を結ぶことなどは求められておらず、したがって、契約を結ぶ病院以外には供給しない、などの制限までは行われてはおりません。
私たちは、ベルケイドについてはそれでよいと考えています。
薬の供給制限などは必要最低限に抑えるべきであり、不要な規制は真に薬が必要な人からその使用の可能性を奪うものになりかねないからです。
患者本人に対する毒性はベルケイドと比べて決して高いとは言えないサリドマイドについては、社会的責任を果たしていない患者さんに対する警告や教育は必要ですが、医療機関への供給制限は不要です。
もし「サリドマイドは催奇形性があり、患者個人の社会的責務の履行を担当医に代行してもらうためには必要だから」というのが、病院に対するサリドマイドの供給規制を行う理由としてあげられるのなら、「何故、患者本人を直接モニタリングするシステムを考えないのか?」を疑問として投げかけざるを得ません。直接的なモニタリングのシステムであれば、特別の契約など、病院単位での薬使用の制限は不要だからです。
サリドマイドの安全管理上最重要な要素である「患者からの直接的なモニタリング」の実施を回避するのは誤りであり、病院に対して契約やその他の厳密な誓約を要求したところで、間接的なモニタリングは直接的なモニタリングに比べれば非効率で様々な問題(契約可能な病院数が限られる/契約までに時間がかかる/問題のある症例が見つかっても原因究明に手間取るなど)を引き起こすことが懸念されます。
| ◎ | 世界標準アジア標準から外れる日本固有の劣ったシステムの導入は世界の笑い者になるだけ。 |
アメリカのセルジーン社とFDAの担当者が頭をつき合わせて練り上げ、その後数年間の実地経験に基づいて改良が重ねられてきたSystem for
Thalidomide Education and Prescribing Safety(S.T.E.P.S.)は、現在サリドマイドなど催奇形性を持つ薬に関する世界標準の安全管理プログラムです。
アメリカだけではなく、ヨーロッパでも現在、S.T.E.P.S.を安全管理の中心にすえたサリドマイドの承認申請が行われています。
また、すでにサリドマイドが承認され、使用されているニュージーランド、オーストラリアでも、中東(トルコ・イスラエル)でも、さらにアジア(タイ・韓国)でもS.T.E.P.S.または、ほとんどそれと同一のシステムの実施がサリドマイドの承認条件となりつつあります。
私どもは、単にアメリカのシステムだから、あるいは、アジアを含む世界で行われているからという理由だけで日本でもS.T.E.P.S.を実施すべきである、と短絡的に主張するつもりはありません。
日本だけで他の国際標準となっている方法と全く異なる方策がとられたからといって、それが本当によいシステムであるのなら、構わないと思います。
しかし、これまでにS.T.E.P.S.が多くの国で取り入れられてきたのは、それが「アメリカ製」だからという理由からではなく、S.T.E.P.S.がサリドマイドの安全管理で最も重要な部分である直接的なモニタリングを可能にする合理的なシステムであるからです。
「日本製」でも、医療機関内で治療を受ける個々の患者さんへの直接的で効率的モニタリングを可能とするシステムであれば問題ないと考えますが、直接的なモニタリングの実施をはじめから放棄する(あるいはプライバシーに触れる事をやりたくないので、担当医に代行して欲しいと責任を転嫁する)システムが導入されようとするのなら、それには大きな危機感を感じないわけにはいきません。
既に各国で有用性が確認されているシステムを無視し、欠陥の明らかなシステムを導入して問題を起こせば、企業のみではなく規制当局もその責任を問われることになるでしょう。
| ◎ | 麻薬管理とサリドマイドの安全管理は異なる。 |
最後に、サリドマイドの管理は麻薬管理の方法を踏襲することで実施されるべきである、との一部に根強い誤った考え方に言及します。麻薬管理とサリドマイドの安全管理は質的に全く異なります。
麻薬管理は、麻薬を使用するべき当該患者以外の者が麻薬を使用する可能性を最小限にとどめることを旨に行われます。麻薬が本来その麻薬を使用することになっている患者にわたるのなら、その患者さん自身に起こること(嗜癖性を含む)自体に対する対処は「麻薬管理」では求められません。麻薬を扱う医療機関内でカギをかけて管理し、台帳に細かい数量管理の結果を記載し、使用後の容器を回収する、などは全て当該患者さん以外に薬が渡らないための方策です。
これに対し、サリドマイドでは当該患者さん以外の者がサリドマイドを使用しようとすることはほとんどありえません。全ての薬と同様に誤用があれば、それは大きな問題をひき起こしますし、万が一、妊娠初期の女性が誤ってサリドマイドを服用する事態が起これば取り返しがつきませんので、残薬の回収などはもちろん重要です。
しかし、サリドマイドで最も重要なのは、麻薬と異なり、本来のサリドマイドを使用するべき患者さんがサリドマイドを使用した後に、その患者さんが、避妊の実施などにより後世代に与えうる影響をどのようにコントロールするかの確認です。一言でいえば、麻薬管理は患者本人以外に渡ることを阻止することがその核となる管理であるのに対し、サリドマイドの管理ではサリドマイドを使用している本人自身が、確かに後世代に対するその社会的責任を果たしていることを確認することが最重要です。